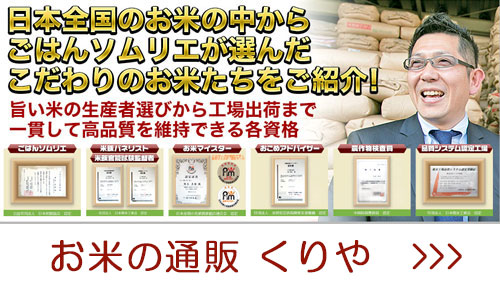「北海道産のお米は美味しいものが多いけど、結局どれがいいのだろう。」
このように、お米選びに迷っている方は多いと思います。
北海道だけでもたくさんの品種があるので選ぶのは難しいですよね。
そこで今回は、北海道産の「ゆめぴりか」と「ななつぼし」についてご紹介します。
□ゆめぴりかの特徴とは?
ゆめぴりかは、過去に北海道大学が食べ比べ実験を行なった際に、7つの銘柄中1位に選ばれたことがあります。
では、そのゆめぴりかにはどのような味の特徴があるのでしょうか。
今までの北海道米にはない味わいを持って生まれたゆめぴりかは、現在ANAのファーストクラスの機内食としても選ばれています。
その味の特徴は、程よい粘りがあることです。
味を左右するアミロースが低いほど粘りが生まれるのですが、ゆめぴりかはアミロースが低いため、粘りが生まれて美味しく感じます。
また、味の良さだけでなく、炊き上がりのつややかさも特筆すべきポイントです。
見た目もよく、味も良いのがゆめぴりかの特徴だと言えるでしょう。
□ななつぼしの特徴とは?
ななつぼしは、北海道で最もおおく生産されていて、生産量と消費量が最大レベルのお米の品種です。
2001年に北海道の優良品種として定められたくらい、味や生産性が優れているのが特徴です。
そんな「ななつぼし」にはどのような味わいがあるのでしょうか。
*ななつぼしの美味しさ
ななつぼしも特A評価を獲得しているため、たくさんあるお米の種類の中でもトップクラスに美味しい品種だと言えます。
粒はしっかりとしており、ほどよい粘りと噛んだ時には甘みが広がるのが特徴です。
比較的さっぱりとした口当たりなので、食が進みます。
また、ななつぼしの大きな特徴の1つは、冷めても味や香りが飛びにくいことです。
美味しさが持続すると言えるでしょう。
*ななつぼしの由来
ななつぼしは、あきほという品種とひとめぼれという品種を掛け合わせて生まれた品種です。
星がとても綺麗に見え、空気の綺麗な北海道で生まれた品種だからこそ、北斗七星のように輝いてほしいという思いを込めてななつぼしと名付けられました。
□まとめ
今回は、北海道産の「ゆめぴりか」、「ななつぼし」についてご紹介しました。
北海道産のお米はたくさんありますが、この2つは特に人気のある品種と言えます。
この記事を参考に、ぜひ気になるお米を食べてみてくださいね。