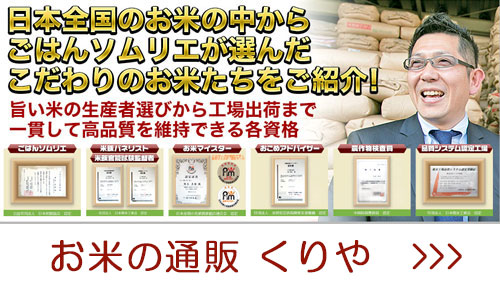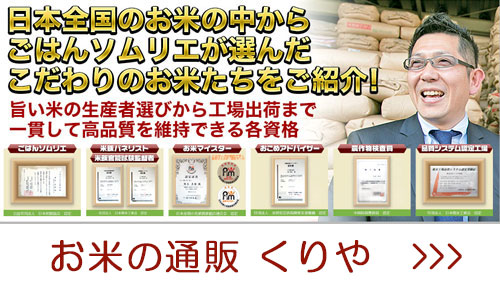皆さんは、普段どのようなお米を食べていますか?
お米が美味しいと、おかずや汁物といった食卓全体が美味しくなりますよね。
今回は、「特A評価」と呼ばれるお米を紹介します。
□特A評価とは何?
皆さんは、食べ物を買う際に、ランクや受賞歴を気にされたことはありますか?
実はお米にも、いくつかの評価基準があります。
特A評価とは、「米の食味ランキング」において、最もランクが高かったお米です。
これは、一般社団法人日本穀物検定協会が行なっているもので、全国各地の代表的なお米が、食味の試験を受けてランク付けされます。
まず、基準米と比較して特に良好なものを「特A」と呼びます。
今年は、全154銘柄の内55銘柄が特Aに認定されました。
中には、何年も連続で特A評価をキープし続けているものもあります。
このような銘柄のものは、プロから見ても美味しいお米と言えるでしょう。
次に、「A」があります。
これは、標準米と比較して良好だと判断された銘柄に与えられるランクです。
今年は、67銘柄がこちらのランクに認定されました。
次のランクは「A’」です。
これは、標準米と比較して同等という意味で、今年は32銘柄がA’と評価されました。
「B」は標準米と比較してやや劣るものに与えられるランク付けです。
それ以上に劣るとされる銘柄には「B’」とされます。
ちなみに、今年はこのランクに評価された銘柄はありませんでした。
今年は、銘柄のおよそ3分の1が、特A評価に認定されました。
このことから、日本の米作りはクオリティが高く、安定した品質の銘柄が多くあると言えるでしょう。
*日本の食味ランキングとは?
特A評価とは「米の食味ランキング」にてランク付けされるとご紹介しました。
この評価基準には、どのような方法が使われているのでしょうか。
実はこのランキングには、厳しい参加条件と基準があります。
まず、評価の対象に規定があります。
それには、都道府県の奨励品種であることと、作付面積が一定以上であることが条件として挙げられます。
つまり、新しく開発されたばかりの品種や少量生産の品種の場合参加できません。
実は少量生産の品種の中にもおいしいお米は沢山あります。
次に、参加条件をクリアした米は指定の炊飯器で炊かれます。
そして、炊き上がったお米は20名の専門家によって評価されます。
この20名は、食味評価エキスパートパネルと呼ばれており、味や香りを的確に評価できるお米のプロ中のプロだと言えるでしょう。
彼らは、お米を次の観点から評価します。
・外観
・香り
・硬さ
・味
・粘り
・総合評価
これらをコシヒカリのブレンド米(標準米)と比較することで点数を出します。
この点数の数値によってランクが決まります。
*ランキングは絶対信頼できる?
先ほど紹介した通り、食味ランキングには厳しいルールが設けられています。
そのため、お米選びの際に参考にされる方が多いのではないでしょうか。
結論を言いますとその年のその品種の評価に対して、お墨付きが出たという安心感がありますが、あまりランキングだけにこだわりすぎず、色々なお米を味わってみるのが良いでしょう。
それは人により、おいしいお米でも「食感の好み」が違うからです。
評価はあくまで試験に使用されたお米の評価です。
そのため、現在、販売されている同じ品種の米に同じ評価がされるとは限らないです。
例えば同じ品種でも、産地が違ったり農家が変わったり、炊き立てより冷めても美味しいことが魅力だったりする品種があります。
さらに食味ランキングに参加していない銘柄の方が美味しいと感じる場合もあるでしょう。
また、日本では日々新しいお米の品種が開発されています。
ランキングにこだわりすぎると、せっかくの出会いを逃してしまう可能性があるでしょう。
あくまでランク評価は判断基準のひとつとして参考にするのが良いでしょう。
□特A評価のお米にはどういったものがある?
日々のちょっとした贅沢や、大切な人への贈り物には、美味しいお米を選びたいですよね。
現在、日本には主食用のお米が300種類ほどあるため、選ぶのは大変でしょう。
次に、特A評価の銘柄を紹介します。
*魚沼産コシヒカリ
コシヒカリは、日本を代表する美味しいお米です。
スーパーやお店で見かけることが多い品種だと思います。
コシヒカリの中でも、魚沼産のものは美味しいと評判の名産地です。
実は、特A評価を通算28回も受賞しています。
この銘柄の特徴は、温度が下がって、冷やご飯になっても美味しさがキープできる点でしょう。
お弁当やおにぎりにしても美味しく食べられますよ。
もちろん、炊き上がった際はふっくらとしていて、北のコシヒカリ特有の柔らかさ粘りも甘味も十分です。
魚沼地域の、夏に昼夜の寒暖差が激しい気候がこの美味しさを生み出す秘訣だと言われています。
これがコシヒカリの粘りやもちもちとした食感を作っているのでしょう。
日本人が好む美味しい白米を食べたい方や、ブランド米を初めて購入する方におすすめだと言えるでしょう。
*山形県産つや姫
皆さんは「つや姫」をご存知でしょうか。
こちらのお米は山形県で生まれた品種で、山形県の奨励品種です。
10年もの時間をかけて開発が行われた品種で、現在は、山形県以外の場所でも栽培が行われています。
しかし、今も山形県のつや姫が、1番美味しいと評判です。
せっかくなら、1番評判が良い産地のものを試したいですよね。
つや姫の、味や食感について気になりますよね。
名前の通り、艶があって粒が揃っている見た目をしています。
味は、甘味と旨味がとても強く、しっかりと弾力を感じられるため、あっさりしていると評価を受けています。
また、旨みの秘密だとされているグルタミン酸やアスパラギン酸が多く含まれているという特徴もあります。
これは、コシヒカリよりも多いと言われており、強い旨みがある銘柄だと言えるでしょう。
一方で、炊き方を変えれば、もっちりとした食感を楽しめるため、様々な楽しみ方ができる銘柄だと言えるでしょう。
*北海道産ななつぼし
ななつぼしという名前を聞いたことがある方は多いでしょう。
これは、北海道で認知度の高い銘柄です。
程良い粘りと艶が特徴で、あっさりしたおかずの味を引き立ててくれる、ひかえめな甘さが特徴です。
あっさりとした味わいであるため、特に和食との相性が良いという特徴があり、つい食がすすんでしまいます。
また、チャーハンやカレーといったお米に味をつける料理との相性も抜群です。
お米だけで食べるのも良いですが、おかずとの相性が良いと、ご飯が進みますよね。
また、評価の割にお買い得な銘柄であるため、普段使いに美味しいお米を探している方におすすめだと言えるでしょう。
毎日のお米が変わると、家での食事が楽しみになりますよ。
自分のお気に入りの米を探してみてはいかがですか。
*宮城県産ひとめぼれ
ひとめぼれは、比較的知名度のある品種です。
スーパーやコンビニで見かけたことがある方が多いでしょう。
ひとめぼれは宮城県で生まれた品種で、コシヒカリと初星を掛け合わせた品種です。
味や粘りのバランスが良いため、オールマイティに使える特徴があります。
特に、粘り気があって柔らかい炊き上がりですので、魚料理や和食にもよく合うと言われています。
おかずに合ったお米を楽しみたいと考える方におすすめでしょう。
□まとめ
今回は、特Aと、特A評価を得たおすすめのお米について紹介しました。
食味ランキングの基準や、評価ランクについてご理解いただけたでしょうか。
本記事を参考にして、ぜひ美味しいお米を探してみてください。