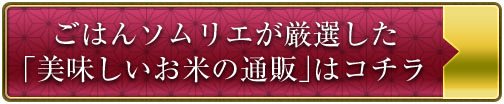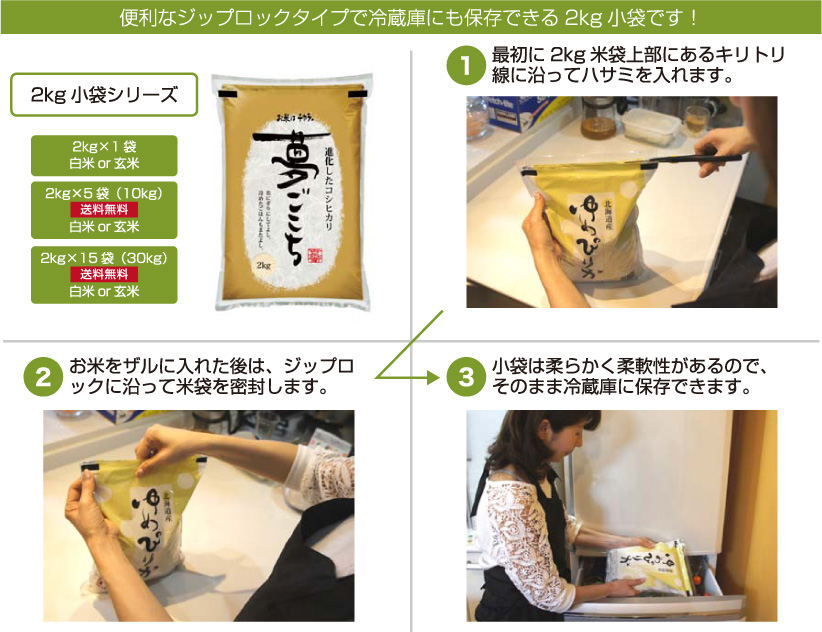「ダイエットをしているから炭水化物で太りやすいと言われているお米を食べることを控えないと」とお考えの方はいらっしゃいませんか?
実はその噂は間違っています!
正しい方法さえ知っていれば、ダイエットをしている方でもお米を食べていただけるのです。
今回はそのような方に向けて、ヘルシーで健康にお米を食べる方法をご紹介します!
〇食事の際食べる順番に気をつけよう
食事をするときに、あなたはどういう順番で食べていますか?
好きなものから食べている方や特に順番を気にせずに食べているという方は、この機会に太りにくい食べ順をマスターしてしまいましょう!
お米が白米である場合には、玄米に比べて食物繊維がないため血糖値が上昇しやすい食品になります。
血糖値が一気に上昇してしまうとインスリンという物質が体内で生成され、血糖値を下降させようと働きかけますが、使い切られなかったインスリンはそのまま体内に残って脂肪と化してしまうのです。
このインスリンの放出を最小限に抑えるためには血糖値を急激に上昇させないことが大切です。
そのためには食事をする際いきなり炭水化物から摂取するのではなく、食物繊維が多く含まれている野菜から食べ始めるようにしましょう。
これだけで血糖値の上昇が抑えられますので、結果として太りにくくなるのです。
野菜を食べたあとは、大豆やお肉などのタンパク質を摂取して、最後にお米という順番を心掛けてみてくださいね。
〇栄養バランスを意識しよう
「お米は太りやすいから食べない!」と決めてしまうのではなく、食事の際には栄養バランスを意識するようにしましょう。
様々な食材をまんべんなく摂取すると、糖質であるお米を摂取していたとしても太りくい体をつくることができます。
もし手料理の時間がとれなかったり、栄養バランスを考えた献立をつくるのが難しいという場合には、サプリメントなどで足りない栄養分を補給することをオススメします。
〇しっかりと噛んで食べる
ダイエット中にお米を食べて良いとはいっても、どんな食材でも食べ過ぎはいけません。
おかずのおともとしてついつい噛まずに食べられてしまいがちなお米ですが、ダイエットを意識されるのであれば、一粒一粒をしっかりと味わうようによく噛んで食べましょう。
こうすることで満腹中枢が刺激されてごはんの食べ過ぎを防ぐことができますよ。
今回はヘルシーで健康なお米の食べ方をご紹介しました。
ダイエット中でも正しい食べ方を心得ればお米を食べても良いのです。
以上の方法を守って是非みなさんもお米を我慢せずに食べましょう!