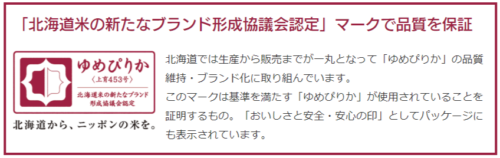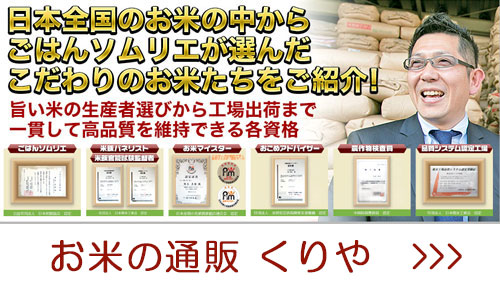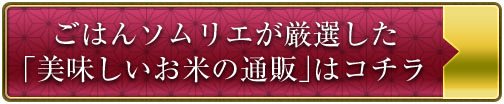有名人(マツコさん?)が出演したCMを見て、ななつぼしについてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
とはいえ、ななつぼしの味がどのような味なのかわからない方も多いでしょう。
ななつぼしの由来や美味しい食べ方について知っておくと、ご家庭の食卓が楽しくなるかもしれませんね。
□ななつぼしにはどんな由来があるの?
ななつぼしの名前の由来についてご存知でしょうか?
ななつぼしの名前は、産地の北海道に由来します。
北海道の気候は空気が澄んでいるため、星がくっきりと見えるのが特徴ですよね。
そのため、ななつぼしは「北斗七星のように輝いてほしい」という願いが込められて名付けられました。
また、ななつぼしはコシヒカリのおいしさを受け継ぐ「ひとめぼれ」と、寒さに強い「あきほ」を掛け合わせて作られました。
特に、日本穀物検定協会が行っている食味試験にて、特A評価を数年連続受賞するほど評価の高いお米です。
□ななつぼしの美味しさを引き出す食べ方
*ななつぼしの味
ななつぼしは、先ほど紹介したように特A評価を連続受賞するほど、人気の高いお米です。
ななつぼしはコシヒカリを親に持ちますが、一部では「コシヒカリにも負けていない」と言われています。
コシヒカリと同様に、程よい甘みと粘りの口当たりが評価されているのでしょう。
食べ心地がよく、味がしっかりしているため、毎日食べても飽きない美味しさと言えます。
*ななつぼしの美味しい食べ方
ななつぼしの美味しい食べ方をご存知でしょうか?
ななつぼしの特徴は、しっかりとした食感とあっさり味です。
和食や古くからの日本料理(お魚や根菜)などに良く合います。
また、粘り気だけでなく、甘さや硬さもちょうどいバランスになっております。
歯切れが良いので、手巻き寿司やちらし寿司などの酢飯にも最適ですよ。
□「ななつぼし」と「ゆめぴりか」に違いはあるの?
北海道産のお米と言えば、「ゆめぴりか」をイメージする方もいらっしゃるでしょう。
両方とも北海道産の「ななつぼし」と「ゆめぴりか」は、テレビCMでも同じようにマツコデラックスさんに紹介されて注目を集めましたよね。
それぞれの味や特徴について知りたい方もいらっしゃるかもしれません。
・ななつぼし:硬さや甘さ、粘りのバランスがよく、さっぱりとした食べ心地
・ゆめぴりか:優しい粘りと食べ応えのある腹持ちの良さが特徴
ななつぼしは、硬さや甘さバランスなど、お米の美味しさを楽しめるのが魅力的です。
一方で、ゆめぴりかの特徴は優しい粘り気がありつつ、粒がしっかりとしているため、食べごたえのあるお米と言えるでしょう。
それぞれのお米にならではの美味しさがあるため、お料理や好みで使い分けることをおすすめします。
□おすすめの炊き方
*お米を研ぐ前の注意点
美味しいご飯を炊くためには、お湯でお米を研いではいけません。
ご飯の甘みは、アミラーゼという酵素がデンプンを分解することで生じます。
お湯でお米を研くと、アミアラーゼが研いでいる間に反応するため、美味しさの成分が流れ出てしまいます。
そのため、お米は常温か冷水で研ぐことがおすすめです。
*計量カップでお米を量り、汚れを洗い落とす
炊く前には、計量カップで適量のお米を量り、お米を洗うことが大切です。
特に、一般的な計量カップは200ミリリットルですが、炊飯器で炊く場合は付属の計量カップで、すり切りできっちりと量ってください。
また、乾燥したお米にはぬかや汚れが付いているかもしれません。
炊く前に汚れを洗い落として、美味しくなるように準備しましょう。
※洗いすぎにはご注意ください。うま味成分も洗い流してしまいます。
*30分〜2時間程度浸水させる
お米を30分〜2時間程度浸水させるのが美味しく炊くポイントです。
夏場は30分、冬場は2時間弱程度を目安に浸水させましょう。
お米が水を十分に吸うと、炊き上がった後にお米のムラが少なくなり、本来の甘みを引き出せます。
*ご飯を中心部まで蒸らす
現在の炊飯器は蒸らす工程もありますので、ブザーが鳴ったら
即フタを開けて、お米をざっくりと十字に切り分け、区画ごとに上下を返すように優しく混ぜてください。
ここで大切なポイントが、ほぐす際に粒を潰さないことです。
しゃもじは押し付けるのでは無く、切るように混ぜます。
□まとめ
今回はななつぼしの味について解説しました。
ななつぼしは、程よい甘みと粘り気が特徴的なお米です。
今回紹介した炊き方や食べ方を参考にしてみてはいかがでしょうか。
当社では、様々な種類のお米を販売しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。